<創刊の辞>
- 真のジャーナリズムとアカデミズムの源流・京都の地から-
岡田知弘 (京都大学名誉教授・京都橘大学教授)
- 真のジャーナリズムとアカデミズムの源流・京都の地から-
岡田知弘 (京都大学名誉教授・京都橘大学教授)
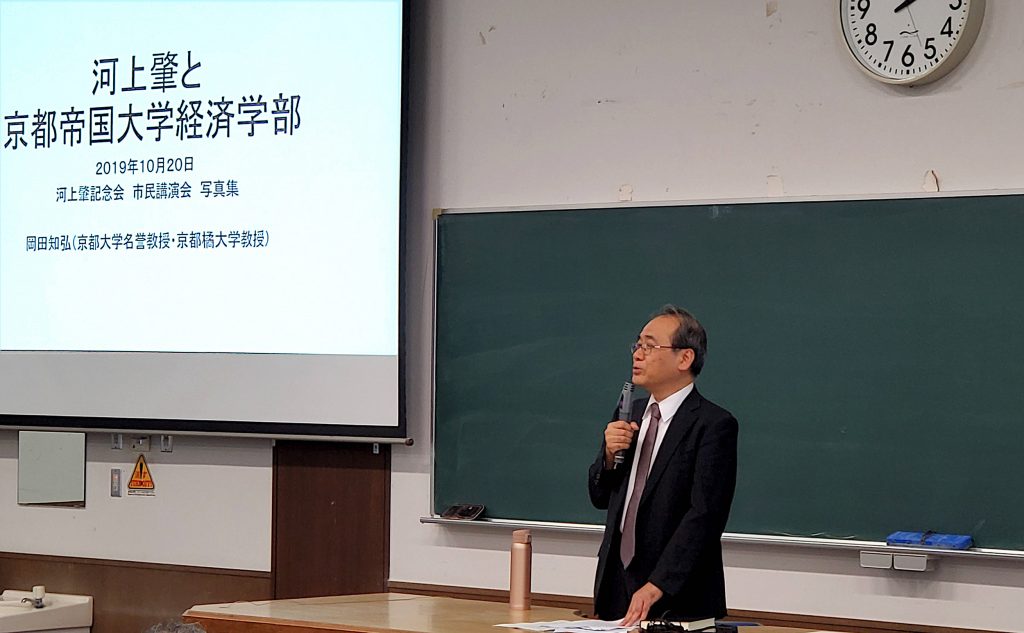
2020年10月初め、第二次安倍晋三内閣を継承した菅義偉内閣が、日本学術会議会員候補6名の任命を拒否する事件が起きた。京都関係者では、京都大学文学研究科の芦名教授と立命館大学法学研究科の松宮教授が入っていた。多くの学会が、学問、思想の自由と日本学術会議の自律性を侵す事件であるとして、任命を要求する声明を発表した。日本学術会議は、今も6人の任命を求めている。その時に、よく戦前の例としてよく参照されたのが、京都帝国大学法学部で1933(昭和8)年に起きた瀧川事件である。当時の鳩山一郎文部大臣が、同学部の瀧川幸辰教授の著作『刑法読本』や講演内容が赤化思想であるとして罷免した事件である。法学部教授会は、教官の人事権への介入であるうえ、学問研究の自由を侵すものであるとし全員辞表を提出したが、後に切り崩しにあい、撤回させるに至らなかった。結局、佐々木惣一・末川博ら7教授が辞職することとなり、抵抗は敗北に終わり、その後、京都帝国大学は政府による戦争動員政策や科学動員政策に積極的に協力していくことになる。
私は、日本学術会議会員の任命拒否事件と比較する際に、瀧川事件の5年前に起きた、経済学部での河上事件も含めるべきだと考えている。この時も、文部大臣が総長に対して、河上肇が危険思想の持ち主なので、辞職させるべきだと勧告し、総長は辞職を要求し、経済学部教授会は、それを黙認することで合意した。それを知った河上が即座に自ら辞職を表明することで、この事件への抵抗は学生たちによる集会程度で終わるのである。
しかし、本質的には、政府にとって「危険」あるいは「問題」と考える大学教員を大学から排除するとともに、その発言を封じ込め、さらに政府に対する批判的な考え方をもっている教員の活動の萎縮をねらったものであるという点では同質の問題であるといえる。この時、経済学部は文部省や大学当局に抵抗することを自ら放棄したのであり、他の学部教員も、「長いものにまかれろ」という思潮が強まり、瀧川事件の際には、法学部教授会に同調した学部はいっさいなかったのである。マルクス経済学者としての河上肇の追放に続いて、政府は自由主義者であった瀧川らの帝国大学からの追放に成功したわけである。
だが、それに満足できない若手研究者集団がいた。京都大学文学部の中井正一(美学)、真下信一(哲学)、久野収(哲学)、新村猛(フランス文学)、冨岡益五郎(哲学)、和田洋一(ドイツ文学)、禰津正志(考古学)といった面々に加え、理学部出身の武谷三男(物理学)も同人となって『世界文化』と題する月刊誌を、1935(昭和10)年2月号を創刊号として、百万遍交差点にあった三一書房から発刊したのである。同誌の編集同人が、1937年11月に治安維持法違反容疑で逮捕されることで終焉を迎えたが、戦時期に至る過程で34号も刊行したこと自体、注目に値する。
実は、この時、中井ら『世界文化』の編集者が拘束されたことにより、ほぼ同じメンバーが編集を担当し1936年7月に月2回発行のタブロイド版新聞として創刊された『土曜日』も強制廃刊を余儀なくされた。こちらの方は、33号まで出版された。
この事件は、しばしば「京都人民戦線事件」と呼称されてきたが、井上史氏が指摘するように、この呼称は当時の警察・検察側が、治安維持法を拡大解釈して事件をでっち上げたことの名残であることに留意する必要がある(井上史編・中村勝著『キネマ/新聞/カフェー 大部屋俳優・斎藤雷太郎と「土曜日」の時代』ベウレーカ、2019年)。

ここで大きな疑問がでてくる。中井たちは『世界文化』や『土曜日』をどのような意図で発刊し、瀧川事件から戦時体制に移る日本、そして京都の地で、何を伝えようとしてきたのか。幸い、最近、井上氏らによる史実の掘り起こしがあり、それを導きの糸にして、『世界文化 復刻』全3巻(小学館、1975年)と久野収編『復刻版 土曜日』(三一書房、1974年)の本文と解説・座談会を読み直してみることにした。そこには、現代の京都で生きる私たちに対する多くの示唆が散りばめられていた。
