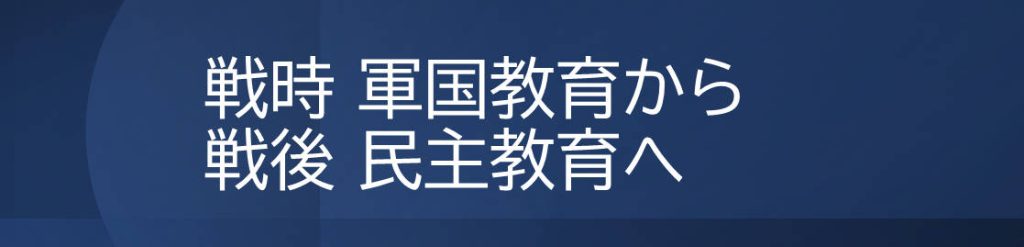
温井 徹念(ぬくい てつねん)さん 91歳
1932年 現在の石川県羽咋郡に生まれる
1951年 龍谷大学入学
1955年 京都府立網野高校網野分校 教師
1993年 府立桂高校を退職
幼少期から青年期にかけて戦争を体験された温井さんが、終戦の混乱した時代、戦後民主主義形成の時代を京都府立高校でどのように生きてきたのかを記憶にとどめ、多くの方に知っていただきたいと思います。
インタビュアー 池田豊(編集部)
― 京都の高校で長年教師をされていた温井徹念さんは、小学生の頃がそのまま戦争の時代と重なっています。当時の様子とその後の混乱期、そして大学生活を経て教職員となり、民主教育の推進に携わってこられた時代についてお伺いしたいと思います。お生まれは?
温井 生まれは1932(昭和7)年、満州事変の翌年です。石川県能登半島の中程にある山村です。当時は羽咋郡加茂村字倉垣と呼ばれていました。現在の北陸電力志賀原子力発電所から東北方向へ12キロ程の所です。
― 生まれ育った家庭はどういった環境でしたか?
温井 家は浄土真宗の西教寺という寺でした。私は長男でしたので本来家と家業を継ぐべきだったのですが、私は放棄したのです。家を出る、村を飛び出すことは大変なことで、後に教員になってから縁を切りました。家を飛び出した後も悪い事をしているわけでもありませんから、雲隠れする必要もなく、それまで通りの下宿住まいでしたが、親から親戚、村のいろんな人まで下宿先に押し寄せてきました。男の子は私だけですから父も必死だったのでしょう。
■小学校時代
― その頃の小学校の様子はいかがだったのでしょうか。
温井 当時の7歳上がりで1939(昭和14)年に小学校へ入学しました。家の隣が小学校でした。入学する前から1年生が学校で一斉唱和する小學國語讀本(サクラ読本)の「サイタ サイタ サクラ ガ サイタ」という声を聞いていました。これが私が入学したときは「ススメ ススメ ヘイタイ ススメ」と、「桜」が「兵隊」になっていました。この頃は「ボクハ グンジン ダイスキヨ イーマニ オオキク ナッタナラ オウマニノッテ ハイドウドウ」という歌が流行っていましたね。歌詞のイメージは乃木大將です。数年経つと、もう「オウマニノッテ ハイドウドウ」どころの状況ではなくなっていくのですが・・。


1940(昭和15)年、小学校2年生のときに国を挙げての盛大なお祝い行事がありました。「紀元2600年記念」行事です。提灯行列に駆り出され「紀元は2600年」と歌いながら村中を回りました。1942(昭和17)年頃だったと記憶していますが、加藤隼戦闘隊が戦闘機で敵機にぶちあたり、ハンカチを振りながら「さようならぁ」・・こういった映像に小学生の私たちは本当に感動したものです。ですから当時の小学生にとって戦闘機乗りはあこがれの存在でした。

東宝製作、陸軍省後援・情報局選定
毎年12月8日の「大詔奉戴日」には全校で朝早くから氏神様へお参りするわけです。お参りが終わると軍人ラッパを吹きながら隊列を組んで学校へ帰りました。ラッパは小学校高学年にラッパ担当の生徒がいました。学校へ帰ると御真影を拝み、次は白い手袋をはめた校長による教育勅語拝読です。子どもたちは寒い暑いも小便をしたいのも我慢してね。そういう時代でした。その頃は紀元節などの式典もあり、紅白のまんじゅうをもらうわけです。そのときは学校が早く終わって嬉しかったですね。
― 戦況の悪化に伴って学校生活はどのように変わっていったのでしょうか。
温井 1943、44(昭和18、19)年になると山奥へ行ってツルハシで松の根っこを掘り起こし、そこから油をとるわけです。シンガポールなどが敵軍に占拠されて石油がまったく確保出来ない状況でしたからね。松の油、松根油(しょうこんゆ)と言うのですが、これで代用するわけです。学校全体の取り組みとして4年生から上の子が山奥へ行って掘り起こすのです。生きている大きな松の根ですからとても重たい。山奥から担いで県道の集積場まで運んでいかされました。
― 当時の記録で「航空燃料として松根油を使った」とあるのを見た記憶があります。
温井 食料事情も悪くなっていくなかで、小学生からするとすごい重労働でした。
いまでこそ笑い話ですが、その当時は全国的に相撲大会が開催されていて、私の住む田舎の学校でも催されていました。その相撲大会では「うっちゃり」とか「肩すかし」といった技は禁じ手でした。そんな技で勝ってはいけないのです。とにかく突っ込んでいく、土俵際で「うっちゃり」で負けても突っ込んだ子どもが勝者です。決まり技は「敢闘精神旺盛」というわけです(笑)。それぞれ地方によって違うと思いますが、私の住んでいた地域ではそんな妙な決まり事がありました。その頃はどこへ行っても「敢闘精神」という言葉が流行っていました。思いつくまま薄い記憶を呼び起こしてみましたが、このような小学校生活が国民青少年の日常みたいなものでした。
■中学から新制高校生時代
― 敗戦色が濃くなった頃に小学校を卒業し、中学に入学されています。
温井 1945(昭和20)年に県立羽咋(はくい)中学に進学しました。千里浜なぎさドライブウエーで知られている町です。年が明けていちばん寒さの厳しい頃に羽咋中学を受験しました。前年7月にサイパンが陥落し、サイパンから米軍飛行機が東京へ空襲に来始めた頃です。試験は口頭試問が主でした。国語や歴史はどうだったか記憶が定かではありませんが、数学は口頭試問でした。そのときの数学の口頭試問が「サイパンから東京まで約3000里、サイパンから時速25キロで走れば東京へ何分で着くか」というものでした。私は適当に答えて会場をでましたから、もうアカンなと思っていました。でもなぜか受かっていました。
― 中学校は5年制だったと思いますが、定員は何人くらいですか?
温井 当時は金沢は別にして石川県の各郡に1校ずつ県立中学校がありました。普通であれば1学校定員150人です。ところが私の受験した時は360人も採ったのです。だから私も入っちゃった(笑)。中学校は5年制ですが、中学3年くらいになると、どんどん陸軍幼年学校、「七つボタンは桜に錨」で知られる霞ヶ浦少年飛行隊などに駆り出されていくわけです。そういったことも含めて360人も受け入れたんでしょうね。
― 羽咋中学での学校生活はどういった状況でしたか?
温井 4月から夏休みまで毎日毎日、しばかれるために学校に通っているようなものでした。旧制高校や大学になると少佐・中佐が配属将校ですが、旧制中学はほとんど陸軍中尉が配属将校でした。それは怖かったですよ。ピッカピカの長靴を穿いてサーベルをカチャカチャと上等兵、一等兵を二人ほど引き連れて威張って来るわけです。教練ばかりですから「気を付け!」で少しでも身体が曲がっているとサーベルで殴られます。これが痛いのなんの。木銃(木でつくった銃)ですが、私たちはこれを槍のように使って藁人形を刺すのです。教練・修身・体育はほとんどそんな訓練ばかりでした。連日、上級生に殴られ、教員に殴られ、殴られ癖がついて少々のビンタくらいでは痛みも感じなくなるほどでした。どんな教員でも殴るのですが、いちばんしんどかったのは癖の悪い教員です。自分が殴って手が痛くなったら、友達を向かい合わせに二列に並ばせて殴らせるのです。手加減をすれば教員にわかりますから、こっぴどい目に遭わされます。だから真剣に殴り合わざるを得ない。これは本当に辛かったですね。
― 戦後世代にとっては映画や小説で知る世界ですね。
温井 その当時金沢の第九師団7連隊という、ちょっと知られた部隊がありました。部隊の兵隊さんの一部が中学校に駐屯するわけです。地域の安全確保といったようなことが言われていましたが、実態は疎開のようなものです。千里浜のなぎさドライブウエーはきれいな長い浜ですから、ソ連が上陸するにはもってこいの場所なのです。ですが、その兵隊の日常生活たるや実に情けないものでした。ダラダラして命令もほとんど行き届かない。入れ墨をした兵隊が軍事訓練をさぼって座っていても上等兵や伍長は注意もしない。もうむちゃくちゃな軍律でした。校舎を歩くとあちこちにノミが飛び散るのが分かるくらい衛生面も悪かったですね。そういった連中が校舎の半分くらいを占拠して常駐しているのです。夏休み前の中学校はそういった状態でした。
― 終戦を前にした軍隊や学校の状況がよくわかります。生徒たちは学校で毎日、何をしていたのでしょう。
温井 その頃はもう5年生はありませんでした。4年生は遠い所へ勤労奉仕。3年生、2年生は毎日、近くの軍事工場へ行かされました。ですから学校へ残っているのは1年生だけでした。上級生が軍事工場からたまに学校へ帰ってくると、ストレス発散とばかりに下級生をむちゃくちゃ殴り回すのです。本当に殴られるために学校へ通っていたような時代でした。
― そして終戦、そのときはどこで何をされていましたか。終戦をどのような思いで迎えたのでしょうか。
温井 1945(昭和20)年8月15日の記憶ですが、晴れ上がった天気の良い日でした。夏休みで私も家にいましたが、たまたま学校がすぐ隣でしたから小さなグラウンドの鉄のない鉄棒の下でたたずんでいました。私は天皇の放送は聴いていませんが、親はもちろん聴いていました。村にはそんなにラジオもありませんでしたが、私の家は寺院でしたからあったのです。以前は短波の入るラジオもありましたが、外国の放送も入りますからすぐに取り上げられました。
正午のニュースが終わって村中が物音ひとつなくシーンとしていたことが、すごく印象に残っています。親から終戦という言葉を聞いて、この国はこれからどうなるのだろうか、学校はどうなるんだろう、明日という日はあるんだろうかーとぼんやり考えていました。絶望を通り越して頭の中が空っぽになった感じでした。
― 夏休みが明け、学校へ行かれて何か変化はありましたか?
温井 9月から学校に行くと教員が半分ほどいなくなっていました。軍隊ももちろんいません。授業が始まっていちばん困ったのが英語の授業が入ってきたことです。1943(昭和18)年くらいから敵性語として英語の授業なんてなかったですからね。野球もストライク、ボールも「ヨシ」、「ダメ」といった言い換えがされていました。それが突然、大文字、小文字に筆記体の大文字と小文字、4つも覚えないといけない。大変でした。
教員もガラッと態度が変わっていました。ですから私はその当時、「教員にだけは絶対になるまい」と真剣に思っていました。夏休み明け早々に、言葉は悪いですが「こんな奴にものを教えてもらっていたのか」とショックを受け、怒りがこみ上げてきたのを覚えています。
― 戦争中は威圧的で暴力的だった教員はいったいどのように変わったのでしょうか。
温井 別に生徒にペコペコするわけではありませんが、例えば、私らをよく殴った教員は生徒の機嫌をとるかのように物腰が柔らかくなって「いまは民主主義だからな」と、そんなことを言っていました。私らの世代は学校には通っていましたが、知識を得られることには恵まれなかった。そのことは悔しいですね。
― 終戦を境に校内や町の様子で強く記憶に残っていることがあればお聞かせください。
温井 予科練帰り、軍隊帰りの連中が復学してくるのですが、彼らは荒れに荒れて大変でした。軍隊生活で覚えた煙草(たばこ)を学校で吸う、教員はビクビクして見て見ぬふりです。町にはまだヤクザなどはいませんが、軍隊帰りといわゆるチンピラと呼ばれるような連中が闊歩して町を押さえているわけです。学校も町も荒れ放題でしたね。ですが、この時期、私はよく勉強はしましたね。
― そして中学校がなくなり、1947(昭和22)年から新制に移行しています。
温井 新制に移行する前段として石川県立併設中学校として1年ほど続き、それから県立高等学校併設中学校に変わっていきました。私たちのように旧制中学からの生徒、新制で入って来る人が一緒になっていました。私たちは新制の高校生を徹底的に見下していましたね。「こいつら無試験で入ってきて、なんやねん」といった差別感がありました。新制は年齢に達したら希望者はみんな入ってきていましたからね。でも新制で入ってきた彼らは真面目で、よく勉強していましたよ。私は旧制で入って新制の3期生として1951(昭和26)年の3月に卒業しています。
― その頃、男女共学に移行していますが、戸惑いもあったと思います。温井さんの思いや校内の様子はどうでしたか。
温井 私が新制の3期生で新制高校の1年になってから男女共学になったと思います。それは戸惑いましたよ、女の人とどんな話をすればよいのか分からないのです。これまで女の人に接するのは母親か姉、妹、親戚のおばさんくらいでしたからね。呼び方も「オイ」と呼べばいいのか「さん」と呼ぶのか、まったく分かりませんでした。男の子はいつまでもモジモジしていますが、女の子のほうはずぶとく、ちゃっかりしています。「○○くん、ちょっと机動かして」と、こんな調子です。でも試験になると女の子はカンニングが多かったような記憶があります(笑い)。レベルが違うのは仕方がないのです。教員もそれは分かっていて大目に見ていました。新制高校の最初の男女共学はそんな感じでした。
― 戦後の混乱期が続き、やがて朝鮮戦争へと進んでいきます。温井さんは高校生ですが、この時代に何を思っていたのでしょうか。また周囲はどのような状況だったのでしょう。
温井 私は高校生でしたが、共産党が非合法化されているなかで1950(昭和25)年朝鮮戦争が勃発しました。「これは大変なことになった」な、と。一言で言えば「また逆戻りか」といった受け止めでした。深く意識したものではありませんが、直感的に「またしばかれる時代になったのか」といった思いは強くありました。小説ばかり読んでいたので哲学や社会科学の知識は私の頭の中にまったくなかったのです。ただ家が厳しかったですし、文学と呼ばれる書物に目を通すこともはばかられる時代でしたからね。詩人、歌人は別にして日本の近代小説家は良識ある人からみると無頼漢みたいな捉え方をされていました。村を出て東京に行き酒ばかり飲んでナンパばかりして、私小説を書いている文学者なんて不道徳そのものという風潮でした。ですから文学と呼べる書物は夜にこっそり読むわけです。 世の中もまだ戦後の混乱が続いていましたし、巷間ではヒロポン(薬物メタンフェタミン)が流行っていました。最初は錠剤でした。注射は禁止でしたが錠剤は結構フリーだったのです。でも錠剤は飲んでもあまり効かない。効いたような気分になって徹夜して本を読んでいるわけです。まぁでたらめな高校生活といえばそれまでです。
■大学生活と高校教員職との巡り会い
― 龍谷大へ進学されていますが、なぜ国文学を専攻したのでしょうか。
温井 1951(昭和26)年4月に20歳で龍谷大学の文学部に入学しました。当時、龍大は文学部しかなかったのです。お寺を継ぐ気はありませんでしたしフランス文学が好きでしたから、勉強してパリに行って遊んで、みたいな程度に考えていました。ですから当時、仏文専攻がなかったので、ほとんど見向きもされなかった国文学を専攻したのです。
大学時代はお酒を飲んで、昼は寝て夜になるとごそごそと蠢いて帰ってきて本を読む、そんな毎日でした。1955(昭和30)年に卒業しましたが、当時は厳しい就職難の時代でした。新聞記者になろうかと思ったものの、朝日・毎日といった大手紙は手が出ませんし、せめて地元紙ならと京都新聞の入社試験を受けましたが、新聞は読んでない、世の中との交流はないわけで無残な結果でした。その頃はまだ家との関係がありましたから、父から仏教関係を勉強するのであれば、あと2年間は学費を出してやると言われたのです。承知して学費を受け取り、学校へ納めに行ったら、たまたま網野の校長がいたのです。前任者である龍大出身の教員が事情があって急に学校を辞めて実家に帰ってしまったので、後任の国語教員を探しているとのことでした。龍大の就職担当の職員が国文学出身の私に目を付けて、話を聞くように勧めるのです。赴任地を聞くと「網野だ」と言うので、「そんなシベリアに近いところは嫌だ」と言ったにもかかわらず、執拗に勧められました。国文学の主任教授に相談すると「君は京都にいたら身体を壊すから、しばらく都落ちしたらどうか」と言われました。言われていることはもっともで、結局、引き受けることになって府立高校教員人生がスタートするわけです。

― 網野に赴任して高校教師、そして府立高教組の組合員として足を踏み出されたわけですが、温井さんには労働組合はどのように映っていたのでしょう。
温井 元々、ヤクザまがいのような生き方をしてきていましたから、労働組合に入ったから、○○闘争だからと言われてもそんなに違和感はありませんでした。網野に行くと「勤務地は夜間の間人(たいざ)分校だ」と言われました。初任給2700円の時代です。給料をもらったら網野本校の組合分会長のような人から「組合費は給料から引いてありますよ」と言われ、「いいですよ」と、何ら疑問もなく答えました。私は労働組合も農協も同じようなものだくらいにしか思っていなかったのです。それが高教組組合員になった第一歩でした。
― 組合員の自覚が出てきて、変わりはじめたのはいつくらいからですか?
温井 そんな私が労働組合と深く関わりはじめたのは2回目の赴任先である亀岡高校時代です。亀岡高校には1960(昭和35)年まで3年いました。網野間人分校で組合に入りましたが、その頃に副校長闘争がありました。当時は副校長や教頭制度はありましたが管理職ではなかったのです。副校長を任命制にして管理職にするというので反対闘争を組んだのです。亀岡時代は懸垂幕闘争や、京教組の初めてのストライキ2・3・5ストにとりくみました。同和教育も意識的に始まっていました。分会長で高教組副委員長も務めていたNという人が亀岡分会や地域の中心的な活動家で、同和教育を担当していました。私はふるい村育ちのせいか同和教育に対して違和感は持っていませんでした。
― 次の桃山高校では相当激務だったと聞いています。
温井 桃山高校に移ってから分会役員をするようになりました。印象に残っているのは、暴力を振るう過激な連中が何度か暴れたことがありましたが、このとき大変でしたね。 家に帰れない日が結構あり、体調を壊して京大病院に入院、退院してからリハビリを含め1年間休職しました。この時期に私自身と周囲の状況から悩みに悩んで家を出る決断をしました。いま振り返ってもこの時期は辛かったですね。
― 1970年代の前半は民主団体全体が全国的に勢いがありました。京都でも「日本の夜明けは京都から」「憲法を暮らしの中に生かそう」を合言葉に活発な運動が展開されていました。この頃は朱雀高校ですか?

温井 1年間の病気休職明けに朱雀高校に復帰しました。直後に1978(昭和53)年の蜷川後継の杉村VS自民党前参院議員林田の知事選挙が行われました。この時、「分会長が先頭に立つことはできないので君がやれ」と言われて、選対委員長を務めました。1日に3回「選対ニュース」を発行し必死でがんばった記憶があります。
私は朱雀高校で分会長を務めました。頻繁に会議をしていたので「朱雀に行くと家に帰るのが遅くなるから朱雀は希望するな」といった噂が京都市内の教員間で流れていた頃です。校長は校長で「朱雀には絶対に着任するな」という話が校長会で流れていたそうです。その後朱雀から桂高校へ異動しました。簡単に言えば追放されたのでしょうね。桂高校には1993年3月まで在職し、定年を迎えました。
― 現在は日々、どのように過ごしておられますか。
温井 握力や筋力は年齢相応ですし声も出ますが、足元が少しふらつくときがあります。本や新聞はまだ読めますが視力の衰えは感じています。でも長野にいる一番下の妹が私を気遣って「もうお酒が切れるころだろう」と実にタイミングよくお酒を送ってきてくれますし、女房の介護のヘルパ-さんが週に1回来たときに、ついでに私のお酒も頼んだり、まぁそんな日常です(笑い)。いまいちばんの悩みは家に積んである本をどうするか、ですね。棄てるのは忍びないし、かといって古本屋もいまは引き取ってくれませんしね。

― 朱雀高校に勤務していた方、関わっておられた人たちが集まって「式部9条の会」を結成されていると聞きました。この名前は朱雀高校の位置する伝統ある地名から名付けられたそうですね。
温井 そうです。この地は平安京において式部省(文官の人事や儀式などを管轄)がおかれていた場所です。「式部9条の会」は8人の世話人を中心に運営され、桂駅付近で世話人会を開催したり、年1回の総会での学習・講演会や伏見戦跡巡りなどを行ってきました。コロナ禍で中断していましたが、いまの状況をみていると「また逆戻りか」と感じさせるような流れが強まってきています。再開する必要があると思います。
― ありがとうございました。
